「364+1」~日常をアートにする下着~
プロジェクトのはじまりは、2019年に行われたケイスケカンダとのコラボレーションによるアップサイクルプロジェクト「ウンナナリサイクール*」に遡る。この企画が好評を博し、すぐに第二弾の構想がはじまりました。二人の度重なる対話の中で、「364+1」のコンセプトが定まっていきました。
*ウンナナリサイクール……ウンナナクールの店頭で販売終了となった商品に、さまざまなアイデアで新たな価値を加え、新商品として生まれ変わらせるプロジェクト。
「364+1」への想い
364のコンセプトも含めて、一度壊してもらいたかった。(塚本昇 )
塚本:当初は、全く別のデザインで検討を重ねていました。ただ、そのデザインは量産の枠組みの中では品質管理を含めて、時間的にもコスト的にも難易度が高かった。結果的にトライアンドエラーを繰り返す中で、その企画はペンディング(先送り)になってしまいました。そこで、ケイスケさんに「364で何かできないですか?」とお願いしました。
ケイスケカンダのクリエーションは、「対象を一度壊して、もう一度つくり直す」というスタイル。その工程を通して新しい命を吹き込むことで、特別な価値を生んできました。364は、僕たちの中でもブランド化していきたい商品です。開発時のストーリーやネーミングに込めた想いをケイスケさんには日頃から話していました。その364を、ケイスケさんの思想と掛け合わせることによって、特別なモノにしてほしい。その想いがありました。
そのとき、神田さんは「364は既に完成している」と言って、塚本さんの申し出を断った。そこには、神田さんの364への敬意がありました。
「壊す」という行為にも作法があって、誰かの想いを壊してまでやることではない。(神田恵介)
神田:まずその対象を壊したいと思うかどうかが大事で。例えば、サイズ感も状態も良いヴィンテージを再構築することは、僕がやるべき仕事ではないと考えます。手を入れずとも、既にそこには価値があるからです。僕たちは、価値がないとされているモノに対して、新しい価値をつけてゆくということをやりたいんですよね。
364はそれ自体に価値があり、そのコンセプトも素晴らしいと思いました。そんな364を僕らが壊して、再構築する意義がそもそもあるのだろうか。364に関わった多くの方の愛情やご苦労を無下にするのではないかと思ってしまって。
塚本:僕はケイスケカンダというブランドが大好きで。例えば、ジャージをジャケットにつくり直したり、リュックサックをトートバッグにつくり直したり。そこには「破壊と再構築」の営みがある。ただ、その“破壊”には愛があります。
ケイスケさんは極力、元の素材にハサミを入れません。縫製を解くことはあっても、「パーツがほしいから」という理由だけでジョキジョキと切り取ることはしない。つまり、愛のある壊し方なんです。素材に対するリスペクトがあるから、再構築する際にもそのムードが現れる。
神田:そんな風に仰って頂き光栄です。一度リセットをかけるためのアプローチ、その壊し方には常に想いを巡らせています。だから難しくもあるし、それが創作のおもしろさでもある。
その対象を自分たちの美学に沿っていかに壊すことができるか考えたときに364は難しいと思ってしまい、一度はお断りさせて頂きました。でも、そもそも塚本社長はもっと次元が上のところで僕らの「壊す」というクリエーションを捉えていてくれていたようです。“愛のある壊し方”という表現をしてくださいましたが、お断りした際に、凄い熱量で切り返しをされたわけです(笑)。
「364」には“1”がない
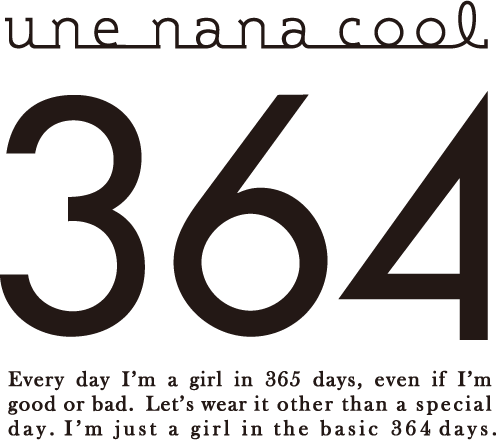
その“1”を、僕が担うことができればいいのか。(神田恵介)
塚本:「364+1」は、単純に計算すれば「365」になる──でも、「365」ではない。
世の中には、「365日」というコンセプトや、「特別な一日」というコンセプトはたくさんあります。それを、あえて「364+1」にすることで、“364”自体をあらためて問い直すことにもなる。むしろ“1”があることで、364がより活かされるのではないかと考えました。それを実現するのは、ケイスケカンダ以上の存在はない。
神田:なるほどそういうことかと膝を打ちました。364のコンセプトは日常に寄り添うもの。それに対して、僕らの服は日常の中の非日常を演出する洋服。日常におけるファンタジーを描きたい。
「364にはない“1”を、364で描いてみてほしい」と仰ってくれた、そのお言葉が深く刺さったんです。「364+1」というネーミングもすばらしいと思いました。何がやりたいか明確な上、“364”自体を良い意味で壊していることにもなる。結果として、364本体にも光が当たり、価値を上げることにつながるのではないかと。
塚本:ブラジャーは機能商品なので、どうしてもフィッティング上の制限があります。最低限のポイントだけ伝えて、「それ以外は商品もコンセプトもすべて壊してもらって大丈夫です」とお伝えしました。
神田:そんな塚本社長の熱い想いに気持ちを動かされました。まさかコンセプトまで壊して良いだなんて。その発想は無かったので慧眼でした。お仕事で一度お断りしたものを撤回して取り組むなんていう経験は振り返ってみてもほとんど記憶にありません。そういう意味でも、今回のプロジェクトは自分自身にとって非日常なものとなった。今回のコラボレーションにおけるまず最初のハイライトでしたね。
「+1」のファンタジー
それは、
着こなしを前提にした下着
極端な話、364をつけて、街に出てしまえるような仕掛けをつくることができないだろうか。(神田恵介)
ブラジャー、ハーネス、ルームウェア。さらには、アップサイクルでつくられた一点物のランジェリー(ガーターベルト、キャミソール、スリップ)たち。受注販売となる364とのマリアージュとしてのトップスとつけ袖。どの商品も364の魅力を引き出し、たたえつつ、ケイスケカンダのファンタジーが息づいています。
神田:今回、下着をつくらせて頂くにあたって、普段アウターをつくっているファッションデザイナーとして、「内と外」の関係性、内なる自分と外なる自分について考えを巡らせました。下着は、その人の肌、そしてこころに近いところにある。それを単なる肌着として“意識しないモノ”にするのではなく、アウターウェアのおめかしをする感覚を取り込んだもの、下着の境界線がゆらぐようなものをつくれないだろうかという想いがありました。
本来、人に見せるべきではないプライベートな存在である下着が、内と外の世界をつなぐような「間」にあるアイテムに。それを下着メーカーであるウンナナクールさんとつくることで、下着業界にはない“下着”になると思いました。「そもそもこれは下着なのかアウターなのか?」という問いが生まれるような特別な存在感をもつプロダクトになってくれたと思います。
“ストラップ”という機能性でしかなかったブラジャーのパーツが装飾性としても生かされ、そこに焦点を合わせてすべて商品へと落とし込まれている。なおかつ、プライベートとパブリックを行き来できる中間を表現したコンセプチュアルなラインナップ。ケイスケカンダの哲学によって、364をクリエイティブに壊し、再構築した「364+1」。そのすべてが、364をたたえる存在としてディレクションされています。
神田:ある意味、これはゼロイチをやっておらず、もともと下着の基本的な構造(ストラップやリボン)に僕たちの色を加えさせてもらってラッピングしたという感覚です。重要なのは、アウター越しにブラジャーのストラップが見えるということ。普通だとマイナスイメージですが、敢えてそれをデザインのポイントにして「ブラジャーのストラップの概念すらも拡張できないか」に挑戦しました。

神田:肩から肩へとストラップを渡し、T字のラインで胸の中央に落ちてくる。アウターの一番上のボタンを開いていたり、ジッパーをおろしたり、あるいはVネックを着ていれば、ストラップがネックレスのように佇むデザインです。


神田:ハーネスは、下着のパーツ(ストラップやリボン)を使った、アウターと合わせるための装具。Tシャツなどの上から身につけることで、「内」の存在が「外」の衣装となる。


神田:ルームウェアは、前回に引き続き「部屋着のまま街に出よう」というコンセプト。フードの紐や羽織のベルトは下着用のパーツを使用して、364+1ブラとセットアップになるような仕掛けに。ルームウェア素材の中でも最上級にあたたかく、もこもこしたボア素材をウンナナクールさんが選んでくださったことで色々奇跡が起きています。
このまま冬の街に出ても、十分な防寒性を有していて、もはやコートとして活躍してしまいそう(笑)。羽織の首元のオリジナルマフラーリボンは、結ぶとマフラーのようにあたたかい。このマフラーリボンは結び方でバリエーションも楽しめるので、着る人自身でお好きなように襟元を描いてもらえたら嬉しいです。




神田:下着のストラップとリボンというモチーフが今回リリースするすべてのアイテムに落とし込まれ、有機的に絡み合い、循環するようなイメージでデザインしました。それぞれのアイテムが家族のような関係性を持っている。内と外の両極を行き来していることで、部屋の中と外の世界をつなぐ。さらにそこには内面という宇宙(ファンタジー)も広がっているような、そんなラインナップにしたいという想いに至りました。
塚本:「+1」をどのように解釈するか。ケイスケさんのすごさはそこにあります。僕たちは「364+1」というお題を出しただけなのですが、ケイスケさんがここまで醸成してくれた。
“ブラジャー”という商品自体が、ストラップやアジャスターなどの装飾性に活かされることで破壊と再構築を起こしていますし、同時に“ブラジャー”や“パジャマ”という概念の破壊と再構築を起こしている。
「+1」が生み出したドラマ
「こんなにも素敵なブランドがあったんだ」ということを伝える一つの手段として。(神田恵介)
一つひとつ手作業の刺繍が施されたアートピースに近いオートクチュールランジェリー。それらは、ワコールから提供された「トレフル」などのブランドを素材としてリメイクされたもの。364と合わせることで、364をより特別なモノにする、まさに「+1」としての存在。「当初、プロジェクトの中でこの話(一点物)はありませんでした」と、塚本さんは話す。そこにはドラマティックな背景がありました。
塚本:ある日ケイスケさんから「364+1」を彩る、スリップやガーターなどのランジェリーを追加で作りたいというご依頼を頂きました。ただ、我々の通常の生産スキームに乗せて1から作るとなると、品質チェックなどスケジュール的にも相当難しい。不可能に近い提案だったのですが、ただ、僕もどうしても見てみたかった──「364+1」をさらに輝かせるためのアイテムを。そこで、ワコールから素材を提供して、ケイスケカンダのスタイル「リメイク」で作って頂けないか提案させて頂きました。
それはまさしく「364+1」が生まれたからできたもの。それなしでは、成し得なかった商品です。
アップサイクルの商品は、ウンナナクールはデザインも縫製も、素材の提供もしていない。提供したのはコンセプトと、ワコールからの素材。デザインをするのも、手を動かして縫製するのも、すべてケイスケカンダ。これは非常に稀有な事例です。さらにそこには、もう一つのドラマがありました。
塚本:個人的に、「トレフル」というブランドに対する想いが強くありました。1977年、ワコールがトレフルを立ち上げた年に、僕も生まれました。そういう意味でも、親近感があった。長きに渡り愛されたブランドでしたが、昨年ワコールはトレフルの生産を終了しました。あと5年頑張ることが出来れば50周年を迎えることができた。半世紀続くドメスティックなブランドではなかなかありません。大切なブランドがなくなってしまったことへの悔しさがありました。
神田:塚本社長からそのトレフルへの熱い想いをお聞きして、同世代の友人として、彼と同じ歳のトレフルという存在にシンパシーを感じ、自分にも何かできないかという衝動に駆られたんです。このままブランドとして消えゆく運命にあるかもしれないトレフルを、我々の取り組みの中で、なんとかつなぎとめることができないだろうか。

今の10代の若い女の子たちはきっとトレフルの存在を知りません。このプロジェクトによってアーカイブのリメイクを世に送り出すことで、「こんな素敵な下着があったんだ」「いつかトレフルが復活してほしい」という声が少しでも上がってくれれば。
伝説のブランドが命を吹き返す可能性はゼロではない。僕らの破壊と再構築という行為には、実は命をつないでいくための祈りのような側面もある。
トレフルの入った箱が事務所に届いたとき、神田さんは涙が出そうになったと言います。そこにはファンタジーが宿されていました。
神田:とにかく圧巻でしたね。トレフルの持つ美しさに見惚れました。その一方で、それがこの時代に合わなくなったという“何か”を象徴しているようにも感じて、なんだか哀しくなったのです。僕はファッションにファンタジーを感じてのめり込み、ファッションに救われ、人生が変わった。そして今、それを生業としています。ただ、時代の流れの中で、ファッションにファンタジー性を宿す素敵なブランドたちが淘汰されつつあることも事実。そこにつくり手として、危機感を覚えています。
トレフルをベースにした作品づくりは、単なる一つのプロジェクトではなく、僕の服づくりにおける人生を振り返るような大きな体験でした。「364+1」をつくる中で、自分の過去から未来へと巡るような旅になるとは思いませんでした。
塚本さんのトレフルへの想いが、神田さんの個人的なファッションへの想いとリンクした。今回のプロジェクトを通して、トレフルにもう一度命を吹き込み、市場へ戻す。二人の想いが、「364+1」に込められ、形となりました。
前例がない下着
アートとしての問題提起
「前例がない」と塚本さんは言いました。オーダーメイドはあったとしても、デザインを含めて一点物のランジェリーを下着メーカーがつくること自体、普通はありえない。
塚本:ケイスケカンダの服には、タグに「one and only」と書かれている。僕はそれがすごく好きで。「これは世界で僕しか持っていないんだ」という特別感がある。まさにアートです。
アートについてさまざまな解釈があると思うのですが、僕は“唯一性”にあると思っています。その極北にあるものが、「one and only」。そういう意味では、ワコールを含めて僕たちウンナナクールの下着は、なかなかアートには昇華できません。量産品なので、アートの文脈でシンクロを生むことが難しい。
その憧れを、ケイスケカンダの力を借りてウンナナクールとしてつくることができた。世界で唯一の商品であり、お客様にはそれを所有する喜びを味わってもらう。それは、その人の思考や人生を豊かにするものではないかと思っています。それが、ウンナナクールを窓口になり得ることができるということは、限りなくうれしいことです。


神田:「364」のような女の子の日常に寄り添う基幹商品をホールドしているウンナナクールだからこそ、「アートへの昇華」を発信することに意義があると思いました。平穏な日常があるからこそ、特別な一日が粒立ってくる。
ケイスケカンダとウンナナクールはある意味、対極の存在だと思うのですが、このような大切なメッセージを届ける時に絶妙な相性だと思っています。
「364+1」を通してのメッセージ

神田:僕らの服は、お客さんたちによく“戦闘服”と言ってもらえることがあって。その人が似合う服より、女の子が挑戦できるような服をつくりたいと思っています。だって、今の世の中には安くてその人に似合うような最適解の服がたくさんあるでしょう。だからこそ、似合わないかもしれない、ともすれば着るのさえ勇気がいる──そこで背中を押せるような存在でありたい。
挑戦することで、その先にはきっと新しい世界が広がっている。今まで自分が躊躇していた服に袖を通すことで、未来が開けることもあるかもしれない。それは「女の子の人生を応援する」というウンナナクールのコンセプトと結果としてシンクロするのではないかと。
塚本:例えば、ブラジャーのストラップが服の端から見えることって、一般的には良くないことだとされています。それをネガティブに捉えるのではなく、むしろアウターウェアとしても楽しめるものへと昇華した。そのチャレンジは、まさに“戦闘服”のようで。女の子たちが「よし、これをつけているから自分は大丈夫だ」と自信を持つことにつながる。女の子の背中を「364+1」で少し押すことできたら嬉しいです。
profile

神田 恵介(かんだ けいすけ)
1976年生まれ。
早稲田大学、文化服装学院卒業。
学生時代からランジェリーをデザインするのが夢で、2005年の東京タワーを舞台にしたファーストコレクションでは、オートクチュールのランジェリーを発表した。
現在は、年に一度の全国ツアーと称した新作発表会を軸に活動。アーティストや企業とのコラボレーションも多岐に渡る。
profile

塚本 昇(つかもと のぼる)/株式会社ウンナナクール 代表取締役社長
1977年生まれ。
大学卒業後2000年に福岡の百貨店、株式会社岩田屋に入社。その後2003年に株式会社ワコール入社。
生産部門や商品営業部、米国駐在を経て2015年より株式会社ウンナナクールに販売部長として出向。2017年より現職。
株式会社ウンナナクールでは『女の子の人生を応援する』というブランドパーパスを達成するべく、既存の下着屋さんとは一線を画したブランディングを展開している。




